|
|
近所にセスナ機が墜落!私は昨夜墜落現場のまさにその駐車場でピアノ教室に行くわが子を降ろし、又お迎えをしていました。毎日通る道沿いに一列10台ほどがやっと止められる小さな駐車場です。今朝も幼稚園正課があり、その時間そこを通るはずでした。プリンターの調子が悪くてもたもたしていたら、停電。セスナ機の主翼が送電線を切った瞬間だったことを知ったのはお昼過ぎにプリンターを運び込んだ電気屋さんでネットニュースを見て。鳥肌が立ち吐きそうでした。自宅から徒歩5分のところです。国立附属幼・小・中学校・国立病院・公務員宿舎・一戸建てが密集している場所で、住民や通行人を一人も巻き込まなかったのはまさに奇跡です。でもセスナ機に乗っていた3人が亡くなりました。
いつ、どんなことになるかわからない人生を思う時、後悔のないように生きなければ、と思います。(毎日、後悔だらけなので、、、)
~本題です。前回、雪かきで時間切れになってしまった部分を今日は頑張って書きます。2時間休みなしに語ってくださった講演内容をつぶさに再現することは難しいのですが、このページを読んでくださっているあなたに、国際化時代を生きるこども達をお持ちの皆さまに、そして留学中のラボっ子に、できる限りお伝えできればと思っています。(もしかしたら聞き間違いや落としていることがあるかもしれませんので、気づいた方は是非校正お願いします!!!)
6、心のやさしさ
~If I wasn’t hard, I wasn’t be alive. If I couldn’t ever be gentle, I couldn’t deserve to be alive.(チャンドラー/プレイバックより~強くなければ生きていけない。しかし優しくない男は生きるに値しない)
・人には優しく!悪いところをけなさない
・相手へ気配りができる人に!日本人は善意はあるのだけれど、表現ができていない。
・先生が親切であるかどうかで、こどもの性格はずいぶん変わる~教育が人生を変える
7、ほめることは伸ばすこと
~アメリカは誉める文化・日本はあらさがし文化
・よいことをみつけて、きっちり褒める。
・名監督は、一日一回必ず女優をほめる。どこでほめるかいつも見ている
・褒めることで人生が変わる ~本人の実力はさることながら、周りがそれをどう受け止め、どうほめてあげるか
*褒め方のコツ→できるだけ簡潔に!「さすがだね」 しかる時→「きみとしたことが・・」
8、余裕のある人生
・もう少し余裕を持って生きよう!~「空海」「良寛」「一休」日本人に人気
・屏風(びょうぶ)人間たれ~一つだけでなく、いろいろもっていると倒れない
~家族があり、仕事があり、好きなことがある人生に!
9、礼儀と品位 ~Guts, Grit, Gumption and grace~
・アメリカで成功する4つのG・・Guts(根性) Grit(度胸 )Gumption(積極性)Grace(優雅さ)
~アグレッシブであると同時に品の良さを身につけさせる。
品位がないと超一流にはなれない
・「朝晩のあいさつ」「ありがとう」は、礼儀の基本 ~アメリカ人は日本人の5倍は「ありがとう」を言っている。
・お土産や高価なプレゼントより、センスのあるThanks Cardを!
~日本人は手土産は忘れないが礼状はない。結婚式にお祝いは出すが帰った後感想は誰も寄せてくれない。講演をしても、拍手はあるが感想を述べてくれない
10、幸福とは何か ~H=((M+2P)÷D+2F+h)h'+2S+D
H=Happiness (幸福) とは、M=Money(お金) と 2P = Position (人に言ってもはずかしくない自分の仕事)とpopularity(人気/どんなに偉くなっても人気がないと幸せとはいえない)を足して、D = Desire(欲望)を割ったもの(50万のお金を得ても、まだ50万かと思うか、50万も!と思えるかでしあわせ度は変わる)そして、
2F=Friend とFamily(良い友人と良い家族)とh=hobby(趣味)を足をたしてh’=healthy(健康)をかける。(どんなにお金があっても欲望を満たしても健康でなければ幸せとはいえない)
さらに2S=State(良い国家)とSociety(良い社会)があり、
D=Disposition(幸せと思える気質)があること。Dは、Destiny(運命/出会い)あるいは D=Dream(夢)とも言い換えられる。
★幸せな人とは、自分を幸せだと思える人のこと。人生は出会い。どんな人に出会ったかで人生は大きく変わる。死ぬ時に自分の人生は満ちたりていた、悔いはない、といえるような人生を送ろう!
|
|
|
|
|
国際社会の中で見えてくる日本・日本人・日本の教育のありかた。そして日本の若者に期待することとは?
ジャーナリストとして世界を駆け回わり、現在もハーバードをはじめ海外の大学で講演をされている松山氏(43年前に初めてアメリカの地を踏んでから100回の渡米を記念して国会図書館に氏のオーラルヒストリーが収録されているそうです。)の豊富な海外経験に裏打ちされたことばの数々と上質のユーモアを交えつつの2時間は、外の雪をとかすほど熱く私の心にしみこみました。
忘れないうちに記録すると同時に皆さんとシェアできれば嬉しいです。
(今日は1~5まで報告します)
1.貴重な若いときの海外体験 ~Read and travel
・頭の柔軟な時にこそ視野を広げる大きな機会
・若い時の1週間は老人の1年に値する
・アメリカを知ると同時に自分の国日本のことを考える良い機会になる
・Read and travel(ハーバードの卒業前最終授業より)本をよく読み、そして社会のいろいろな人に接することが大切。travelは、なにも観光旅行せよということではなく、体験せよ、ということ。本や写真だけではわからない「緊張感」や、自分自身で見て感じ取って「実感する」ことが財産。
2.もっとたくましくなろう
・日本の秀才達は甘やかされすぎて、逞しさがたりない。挫折に弱い。マナーが身についていない
・日本の教育は負けると怒られる。アメリカの教育は負け上手をつくる・・人生は負けることのほうが多い。挫折からどう復活するか。set backからover come~そのトラブルをどう乗り越えたか(ハーバード入学試験口頭試問より)
”Tomorrow is another day”/風と共に去りぬ ”Sweet are the uses of adversity”/逆境の中から甘いもの/シェークスピア・・順境からは何も育たない。勝利よりも敗北から育つことのほうが大きい。
“Let’s go whistling under any circumstances” /ネーテイブアメリカン伝承・・うまくいかないから、と、人のせいにしたり愚痴ったりしないで、どんな環境にあっても口笛をふいていこうよ!
3.自分の意見をもつこと、と魅力的な発表力
・「君の頭の中には脳がある。君の靴の中には足がある。君は君の選択に従ってどの方向へも行くことができるのだ」(ヒラリー・クリントンの座右の銘)・・要するに自分で考え選択し自分で行動することが大切。
・日本ではたくさんの知識をもつことを教育されているが、国際社会の中ではいくら知識や教養があっても、自分の意見をもたない、あるいはもっていても人を惹きつけられるように発表・表現できないと認められない。
・日本人は平均的を好むが、欧米では自分の目玉、売り物を持つことが尊重される。ユニークは素晴らしい!
~この人間は何を発信できるのか、どんな意見をもっているのかが問われる。
*判断力と表現力。自分の意見をもちそれをいかに楽しく魅力的に発表できるか。欧米ではユーモアのセンスと魅力的な表現力を幼い時から身につける教育をしている。ex: Show and tell
4.外国語に強くなるには
*イエール大日本語学科の生徒の日本語が上手になる気質から~
①しっかりした動機付け・・その言語を習得して自分は何をしたいのか?何を伝えたいのか?
②間違いをおそれない・・失敗をたくさんしたほうが早く上達する(日本人は間違えるくらいなら黙っている)
③内容が勝負・・・発音や文法よりも相手とのコミュニケーションは内容!
④自らを窮地に追い込む・・苦労して初めて身につく
⑤サービス精神・・相手の立場に立つ/おもいやり・やさしさが大切。
⑥素直さが大事・・文法にWhy?を持ちすぎない。
5.明るい気質、表情が大事
・日本人の形容詞 3つの”D” から 3つの良い“D”へ~
①Dull-たいくつ②Difficult(気難しい)③Diffident(自信がない/おずおずした)
→①Dynamic ②Delightful(愉快、周りの人を楽しませる)③Dignified(品位)
*知的なユーモアと気の利いたウイットは、日本人が考える以上に欧米で大切にされ、人との大事な潤滑油になっている。笑いがわかるということはとても大切~笑いの反応で聴衆のレベルがわかる。
*******
6、心のやさしさ
7、ほめることは伸ばすこと
8、余裕のある人生
9、礼儀と品位
10、幸福とは何か ~次回報告します
☆松山幸雄氏・・1930年東京生まれ・東京大学法学部→朝日新聞・ニューヨーク支局長(71-74)→アメリカ総局長(ワシントン74-77)→論説委員(77-83)・論説主幹(83-91)・論説顧問(91-93)を歴任
現在・国際大学理事・ハーバード大学国際問題研究所評議員・(財)ラボ国際交流センター評議員など
********
あらためて、昨日の公演内容を書き出してみますと、やはりラボ活動は「国際社会でのびのびと自分を表現できるようにしていく教育」だということがよくわかります。
ダイナミックさも逞しさも判断力も魅力的な表現力も、ユーモアのセンスも、品格も、付け焼刃で身につくはずもなく、つまり、幼い時から時間をかけて育てていくことが大切なんだと実感します。
豊かな人間関係、豊かな教育環境の中で育てたいと、こどもを持つ親なら誰もが願うこと。ラボの理念がひとつひとつの活動の中で確実に実践できるように、そして一人でも多くのこどもたちが、Dynamic、Delightful、Dignifiedを兼ね備えた国際人となるように、パーティの充実とラボっ子の仲間づくり、、、頑張りたいな!!と思う総会でした。
雪化粧の富士山、美しかったですね。
|
|
|
|
|
ひろば@をご覧になっている総ての皆様へ メーリー・クリスマス!
8月のひろば@デビュー以来、PCの前に座るのがすっかり日課(なかば中毒?!)になってしまい、余計忙しく自分を追い込んでしまった私ですが、このひろば@を通じて、たくさんの出会いがあり、多くの励ましや示唆をいただくことができました。本当にありがとうございました。(家族のみんな、洗濯やまもり、ほこり山盛り状態でも我慢してくれてありがとう!感謝、感謝。)
もしかしたら出会えなかったかもしれない遠方のラボ・テューターの皆さんや、なかなかゆっくりお話できないお母様方やOBのみんなや、「ラボって何?」って興味しんしんのビジターの方々とこうしてこの場で交流できたことは、大きな喜びとなりました。
その、総ての皆様に感謝の気持ちを込めて山梨より
  
皆様にとりまして最高にHappyなクリスマスになりますように!
そして、こどもたちのために世界に平和が広がりますように!
~来年もどうぞよろしくお願いします。
|
|
|
|
|
およそ私の知ってる限り他の英語教室では、真っ白なノートに絵を描くような時間のかかることはしない。せいぜい塗り絵をするか、決められた場所に決められた内容を写す程度だ。しかしラボ・パーティではよく絵を描きます。
英語を習わせているのに、何で絵を描くんだろう?と疑問に思う人もきっとおられるだろう。他のテューターは、絵を描くことの意味をどんなふうに親に伝えているんだろう?
そして、幼児をもつラボ・ママたちは、その活動をどう捉えているんだろう?
先日のパーティで『We're Going on a Bear Hunt』に取り組んだ時、
「各場面の絵があったほうが小さい子はわかりやすいし、物語の中にはいりやすだろうから」って、ラボ・ママが、家で子供と一緒に描いた全場面の絵を届けてくれた。模造紙に一枚ずつ、絵の具で描いてある大作だ。相当時間もかかっただろう。でもその絵を描いている間中、ラボっ子はず~とクマがりの世界に入っていただろうし、絵本のひとつひとつの景色が、目の前に立ち上がり広がっていく様子を実感しただろう。なにより大好きなママが一生懸命に自分や、みんなのために丁寧に絵を描いている姿を、こどもはどんな気持ちで見つめながら一緒に描いていただろうか。想像しただけでもあったかい気持ちになってくる。その子にとっても「特別な物語」になるに決まっている。
そのママが、私に言った。「どうしてラボ・カレンダーの絵って、あんなに力づよいのか、どうしてあんな色が出せるのかずっと不思議だったんです。それにラボっ子って絵本を見ないでもさっさっと絵を描けるようになっちゃうことが不思議でした。でも今回、自分が描いてみてやっとわかったんです。物語が身体にしっかり入っていないと絵は描けないということを。物語の中のことばがしみこんでいるから、ああいう絵や色になるんだということを。
私が「川」を描いた時、はじめは、川だから「水色」って、ただ塗っていたんです。でもCDを聞いて、見ると、ただの水色じゃあ"deep cold river"にならないんです。「森」の時も、「ああ、森だから木がいっぱいある」って初めは木だけ描いたんです。でもそれだけじゃあ「深くて暗~い森」には見えないんです。絵を描く時、ラボっ子ってその場面をものすご~い勢いで想像しているんだって、そしてそこにある言葉がしっかりとイメージされ描く場面にちゃ~んと投影されているんだって。一枚の絵でもそこにはずっと広く物語やことばが連なっているのだということがよくわかりました。そして絵を描くことによって言葉も物語もさらに鮮明に自分の中に焼き付けられていくことを実感しました。」
****
Educationと同じ語源をもつeduceは、潜在する性能などを引き出す=drow outという意味があります。つまり、教育とはこどもたちに何かを与えることではなくて、こどもたちの中にある能力を引き出す活動であるということです。
ラボのプレイルーム年代(0才~3才)では、まず、人間も含めた「環境との自然な対話」の時期であるとし、何かを積極的にeduceするその前に、成長のための環境を準備することだと捉えています。ですので、こどもをとりまく最大の要素である【お母さん】を活動のもう一人の主人公として、お母さん自身も体験を通して学ぶlearning by doing を目指しています。そして、お母さんとこどもの関係、からだとこころのつながり、こころとことばの土台をよりしっかりさせていく活動でありたいと思っています。
親子で楽しむプレイルーム活動は期間限定です。今だからできること、今しかできないことを大切に、今、このときを、良質な絵本に囲まれて生き生きと活動できる親子はなんて幸せでしょう!とつくづく思います。
そして、やがてプレイルーム活動を卒業する時期がきても、いつまでも「ラボっ子の強力なサポーターであって欲しいな!」と心から願っています。
***
・・・・・と、また長編になってしまった!最後までおつきあいくださってありがとうございました。「何故、絵を描くんだろう?」それぞれの体験談がシェアできたら嬉しいです。
|
|
|
|
|
11月24日甲府市総合市民会館・芸術ホールにて山梨地区テーマ活動発表会が開催されました。山梨地区で活動する7パーティから150人を越えるラボっこがステージに立ち、テーマ活動やナーサリーライムひろばで大活躍!
ギルガメシュは、前半4番目の発表でした。司会者が「次は間瀬パーティです。こんかいは~~」のコメントを言っているとき、緊張は最高潮。自分が出るわけでもないのに異常な興奮状態!ホント、何回やってもなれないなあ~。胃も心臓にも良くないです。
でも私は、その瞬間のみんなの顔が好きです。きりっとした横顔、ライトに照らされたキラキラした瞳!ステージ上では、テキパキテキパキ、あっという間にスタンバイ!あまりの頼もしさに、みんな大きくなったなぁ~って、いろんなことがフラッシュバックして、始まる前から感無量!!オープニングの音楽がなり始め、タイトルコールが聞こえた瞬間、涙、涙です。
今年は、新しい挑戦でした。今までは、セリフで物語が進行していくテーマがほとんどでした。会話が多いと「見る側もわかりやすい」「セリフは感情移入がしやすい」「掛け合いが楽しい」「センテンスが短いから覚えやすい」「CDの音声から、性格も気持ちの動きも読み取れる。」などなど、私も軽快なテンポの元気あふれる物語が大好き!
けれどギルガメシュは、「全部説明されているから、自分のこととして捉えにくい」「本当は『ギルガメシュは幸せではありませんでした』なんて思っていないかもしれないのに、それをどうやって表現するの?」「こころとはどういうもの?」「好きになりました」「ともだちができたのです」って、どうやってそれを表現するの??? 幼児+小~中2には難題だらけ、課題は山盛りでした。
そこで、登場人物に少しでも自分を重ねられるように、ちょっとスクリプトを変更しました。(ライブラリーそれ自体が一つの芸術作品だと私は思っているので、そういうことは今までしたことがなかったし、これからも多分ないと思いますが・・・)
説明調を自分のことばで言えるようにしました。
「~といいました。」の前の部分は、その人物が言おうよ!ってことになり、「~といいました」の説明はいらないね。っていうことです。
ナレーションに組み込まれている部分、例えば"The hunter said that he could not capture so strong a wild man by himself"をセリフとして独立させるためには、どのことばを落として、どこをどうかえなければならないかということも考えました。 しかし、
特に幼児・小学生はCDから音だけで覚えているため、ことばそのものを変えてしまうことは危険でしたので、シャマト役(小4)の部分、特に”Enkidu must not go near the city of Uruk where Gilgamesh was waiting to destroy him”は、文章ことばではありますがそのまま言うことにしました。でもやっていくうちに、シャマトが直接いってるんだから、“him”はおかしいよ~って意見もでてきて、、、小さい子たちには、「なんでかな~?」の世界でしたが、高学年にとっては、ちょっと立ち止まってことばに向き合う、貴重な時間となりました。
*******
例年、自分のパーティの発表の時は、客席で全体をしっかり見るのだけれど、今回は多少セリフに替えたとはいえ、やっぱりほとんどがナレーション。万一、そのナレーションが一行でもすっ飛んだら、場面ひとつ簡単に抜け落ちてしまうことも十分に想定でき(発表2日前の最終リハーサルで初めて皆のナレーションを聞けたような状態だったし・・全員揃っての練習もとうとう1回もできなかったし、、、だいたいテーマ決定から1ヶ月半しかなかったし・・・と、まあ次々と言い訳も浮かびつつ、)舞台下手のナレーションマイク前に陣取り、今回はプロンプターに徹しようと覚悟を決めていました。
しかし自称プロンプター(私)は、相変わらず忙しくて、客席の元気印ラボっこに注意をしながら写真は取るわ、隣に座った子からの「カリウドってなに?」「あれはお城か?」との質問にも返答するわ、全体も見つつ、で、結局プロンプターは全く役に立たない、というか、お呼びでありませんでした。
つくづくラボっこは、すごいな~って実感です。今回は私が最後のテューターごあいさつを担当したので、皆と同じステージに立ちました。ステージ中央でお辞儀をし、顔を上げた瞬間、あまりのライトの明るさに目がくらみ、思わず真っ白になってしまった私とは雲泥の差。ラボっ子の勇気・逞しさ、仲間の力、自己表現力・協調性・独創性・・・(あ~書き出したらきりがない)すごくたくさんの生きる力を獲得しているな~と嬉しくなってきました。
芸術ホールは、私にとって憧れのステージでした。「いつかこんな大きなステージにラボっこを立たせてあげたいな~」「ひろ~い舞台でのびのびと発表したら気持ちいいだろうな~」って、何十年も思い続けてきました。
だから当日はもうそこに存在するだけで胸がいっぱい。嬉しくて誇らしくて、、、やっとここまで来れたという万感の思い!お花なんかいただいちゃったら、も~、ホールの高い天井も突き抜けんばかりに舞い上がってしまいました。
頑張ったラボっこたちへ!素敵な発表をありがとう。一生懸命なあなた達の姿は本当に美しい。伝えようとするその心は深く尊いものです。応援してくださったご父母の皆様、テューターの皆様、ありがとうございました。又、次なるステップに向けて元気よく飛び立てそうです。
*******
あ~ またしても長編日記になってしまった!
最後まで読んでくださった総ての皆様に、
「感謝の気持ちでいっぱいです。」
|
|
|
|
|
発表会前の余裕のなさと画像取り込みに四苦八苦していた都合でなかなか書き込めなかった「ギルガメシュ王ものがたり」その後。遅ればせながら報告します。
11月初旬。やっと「資料集」完成!ギルガメシュ発表メンバーのうち、小2から中2までが、それぞれ自分で研究テーマを決めて報告、各自レポートにまとめて提出したものを一冊にまとめました。全54ページ!製本も大変でした。しかし、いそがしいこども達が図書館にいったり、本を探したり、まとめたり・・の作業はもっと大変。お手伝いしてくださったご家族の皆さんも否応無しに「ギルガメシュ」に巻き込まれていきました。(さぞ大変だったこととご推察いたします。すみません、いつも親掛かり、大掛かりになってしまい・・・)
CONTENTS*****(抜粋)
・メソポタミアってどこ?~シュメール人の都市国家 (K・小3)
・文明のはじまり①~シュメール人が発明したもの (S・小5)
・文明のはじまり②~学問の発達 (K・小4)
~くさびがた文字の変革 (R・小4)
・メソポタミアのたべもの (H・小2)
・ウルクの二つのジッグラト (H・小6)
・ギルガメシュ王について① (Y・小3)
・ギルガメシュ王について②~叙事詩の発見 (M・中1)
・人面有翼像について (N・中2)
Pick up!
*ウルク(紀元前3500年頃)の二つのジッグラトについて(Thanks Hiroto!)
・都市国家にはそれぞれ守護神がいて、ウルクには二つの「ジッグラト」という守護神の神殿がつくられた。
①エアンナの聖域・・・祭られているのは、イナンナ(女神・のちにイシュタールと呼ばれる女神)聖域の中心にジッグラトがそびえていた。今でも、レンガで築かれた基礎部分が残っているため、自然の丘でなくレンガを一ずつ積んで造った建物であることがわかる。斜面には所々むしろが顔を出す。レンガの水平を確認するために入れられたものらしい。
②クッラブの聖域・・・シュメールの建物はほとんどがレンガだが、このジッグラトは石造り。南イラク(南メソポタミアではほとんど石がとれないため、交易によって別の場所から持ってきたものと推測できる。)建物の構造は石の壁が三重で迷路のようになっている。こうした建物はメソポタミアでは他にない。
⇒⇒表現として、エンキドゥが初めてウルクの都を眺めたその情景の中に、これらのジッグラドを描写した。
*人面有翼像について・・・(フッキーが調べてくれたものです)
絵本では~So it was that Gilgamesh ordered a great wall to built around the city~の右側のページに登場。ウルクの人々が懸命に引っ張っている翼がついた巨大な像の名前は有翼人面牡牛像(ラマス/Winged Bull)といい、アッシリアの守護神。牛の角の形をした冠をいただき、ひげのはえたいかつい顔、胴体は牡牛、背中に翼。ラマスが人間の顔を持つのは、知性を表わす。背中の翼は王鷲の翼。牡牛の胴体の意味は豊穣。門の入口に置かれているのは悪霊の侵入を防ぐため。足が5本ある。何故5本足か?・・横から見ると歩いているように見えるため、味方の士気を鼓舞させるように、前から見るとどっしりと4本足に見えるのは外敵を威圧するため。アッシリア美術の高度なテクニックである。(絵本最後のページには3頭のラマスが登場している・・・さて足は何本か?)
ルーブル美術館蔵(大英博物館蔵のものは現在、東京都美術館に展示中)高さ4・4㍍ 重さ・・ロンドンバス2台分(こんなにとてつもなく大きく重いものを、どうやってウルクから大英帝国に運んだんだろう??)
⇒⇒11月中旬・・・Tシャツを急遽作ることになって、デザインをヒロ(高3・休会中)に頼んだら、偶然か必然か、このラマスの絵を書いてきてくれたのですぐ決定!字体は、リハーサル中のこども達の横で、お母様方がお習字で書いてくれた。その字をパソコンに取り込みデザイン化して決定。 重みのあるTシャツになりました!!
★さて、ラマス。東京都美術館に行かれた方、実物はどうでしたか?・・やっぱり自分の目で見てみたいな~
字ばっかりでお疲れ様、やっと画像登場!
11月初めの合宿の時のものです。小グループで、話し合ったり動いたり!

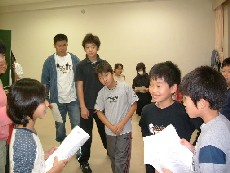
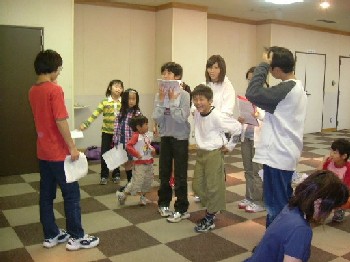


さ~て、このどやどやが、発表当日、どうなりますか。近日画像公開!
|
|
|
|
|
ラボを始めて、20年になりますが、3年目あたりで、楽しいのはいいのだけれど、「本当にテーマ活動で言語が習得できるんだろうか?」と、ふと不安になったことがありました。
今日は、ちょっと長くなりますが、ラボではなんで英会話じゃなくて、テーマ活動をしているのか、少しでも参考になればと思い、私の体験を書いてみます。
どうぞおつきあいください。そしてご意見を是非!!
私がラボを始めたばかりの頃は、ただ楽しくて楽しくて、毎週のラボの日が待ち遠しかったし、最初の5人のラボっ子と1回のパーティで2つのテーマ活動をしていたほどでした。でもはたから見ると、どうみても「遊んでいる」としか映らないのです。保護者の方々もきっとあまりにラボが未知数(そのころ山梨には、ほかにパーティがなく、モデルとなる大きな子も知らなかったの)で、「ラボって何ぞや?」っていう不安から、「忍耐」もしくは「期間限定」でおられたかと思います。
私も考えました。このままラボを続けようか、どうしようか。
そこで、私はアメリカに行くことにしました。アメリカの教育現場に興味がありましたし、なによりアメリカの子が実際にどうやって英語(母国語)を学ぶのか、どのような言語教育が施されているのか。また、もしアメリカの小学生が日本語を学ぶとするなら、どのような手段が有効か、自分の目と耳と身体で絶対に体験したいと思いました。
それからあらゆるツテを頼ってなんとか、公立の小学校の教壇に立てることになり、その頃いたラボっ子は新しくできたパーティに一年間だけ代講をお願いして出発しました。
赴任先はアメリカ東海岸、ヴァーモント州(ニューイングランド地方)の2つの公立学校でした。前半は、1年生から9年生の日本の小学校と中学校をあわせたセントラルスクールです。
そこではイマージョン教育の前段階、今でいう総合教育が実施されていて、それは第二外国語を選ぶ前に世界の主だった国について、その国の先生からその国について学ぶというものでした。また、日本では教科ごとにやっていることが違いますが、ここでは教科横断が見事に実践されていました。例えば半年間は日本の社会・歴史・言語・美術・音楽・クラフト・ダンス・・などをトータルに学ぶことができます。その後に、第二言語を選択できるので、その国の言語を学ぶこども達のモチベーションがしっかりしている、というのが印象的でした。
私はそこで、教科:日本語を担当しました。私は日本語のネイティブです。しかし、どうやって教えたらいいのか悩みました。いかに楽しく興味を持って学んでもらえるか、そして、いかにやさしく日本語を習得してもらえるか・・・
すでにラボ・テューターとして日本で「テーマ活動」をしていましたので、ラボの「テーマ活動」が果たして、アメリカのこども達にもできるのか、そして、それが言語習得の道として有効か、実践してみることにしました。
教科のほうは、学年に応じて会話を中心に教えることになりましたが、その他5~6年生の選択科目で、2クラスの「日本語会話」(どんなカイワをするんでしょうね!日本語会話を習うって、なんか変な感じでしょう?アメリカ人からすると日本人が『「英会話」を習う』とうのも同じように違和感があるようです。)も担当することになりましたので、ひとつは、「テーマ活動」を、もう一つのクラスは、まさしくダイレクト・メソッド、(まあいわゆる、英会話学校で外国人の先生から英語のみで学ぶと同じスタイル)で各3ヶ月間実践しました。
テーマ活動のほうは、「ももたろう」です。英語と日本語のバイリンガルテープを学年主任の先生と私で作り、4月から取り組み、夏休み前に全校生徒と保護者の前で発表することを目標にしました。
もう一つの会話クラスは、ある日常の状況を設定して、その状況に応じた会話を覚えていくというものです。会話はひながたを、担当の先生と設定して、ワークシートを使って(ますます英語学校のような日本語クラス)、書くこと、読むこともいれました。もちろん全部日本語です。
さて、「ももたろう」。なんで、おばあさんは川で洗濯なのか、なぜこんなに大きい桃が流れてくるのか、なぜ、だんごほしさに、鬼たいじに行くのか、いちいちおかしいわけです。いつも教室には笑いが広がりました。で、疑問を解決するために、日本について調べてきて発表する。着物の着方も習ったり、そのうち音楽を用意してくる子もでてきて、BGMと効果音もでき、衣装も作る子がでてきたり、皆で桃太郎の桃マークのはいった「のぼり」を作ったりしながら、ずっとテープをかけて聞いていました。そうすると、そのなかで、セリフが自然に口から出てくるようになったのです。そしてそのことばは、日本語ネイティブの私を唸らせるほど美しい発音なのです。少しできるようになると、セリフを言うのが楽しくなり、さらに、「川の水は冷たいと思うから、そのときなんと言えばいいか」とか、「帰ってきた桃太郎を誉める時には日本語ではどういうのか」といっぱい聞いてくるようになり、それをどんどん日常生活に入れていくのです。
一方、会話クラスの方は、お勉強スタイルで、
まさにrepeat after me の世界!「教える・習う」授業です。また、日本語のダイレクトなので、簡単なことばも伝えるのに時間がかかりました。それでもたとえばレストラン編として、動きをつけて、メニューもつくり、お客とウエイトレスなどに設定してあげると、とたんに楽しくなるのです。でもそれも1回制のものなので、すぐ忘れてしまうのです。
結局、一年後私が帰国する時に、日本語が定着していたのは、「ももたろう」に取り組んだこども達でした。一つのことを同じ目標を持って取り組んだメンバーは、私にとっても特別近しく感じられ、お互いに心が通じ合えたような気がしましたし、今でもとてもあたたかい気持ちで思い起こすことができます。
「ことば」を学ぶということは、まず、心が開放された時に学べるのだと、強く思いました。
もしあの時、会話中心のクラスが成功したら、私はラボを選ばなかったと思います。
でも、今もラボを続けているということは、【物語】がどんなに大きな力をもつか、それを表現する【テーマ活動】を取り組むことによって、こどもたちの心の深いところにまで到達することばが獲得できるということ。また、物語まるごとは、より多くのことば、洗練されたことばにたくさん触れることができ、ストーリーが深く刻み込まれるため、時間が経っても忘れない、、、つまり、うわべだけの「英会話」では太刀打ちできない。ということがわかったからです。
「ももたろう」をしていた子が、なぜ、次々にことばを覚えて言ったかというと、それは自分たちが主体的に作り出していくときに必要だったからです。それに、たくさんの発見があったからです。ひとつのことを目標を持って仲間と取り組むことによって、やる気もおき、いろんなことを調べて、また、新しい発見をする。どきどき、わくわくしますよね。新しいことばをおぼえるということは、どきどきわくわくするほど刺激的なことなのです。repeat after me では、発見も喜びも限界があるのではないでしょうか。
日本にはたくさんの英語教室があります。私もラボを始める前にたくさん見て歩きました。
大切なのは、こどもたち自身が主体的な活動になっているかということだと思いました。
私達親は、お金を出しているんだから、その分、教えて欲しいとつい思ってしまいますね。でも、教え、教えられる関係は、いつまでもそこから脱しえないので、いつかこどもは、つまらなくなってしまうのです。
言語習得は、そんなに簡単なことではありません。ちょっとやったからといって、「ぺらぺら」にもなりませんし、すぐに結果がでるものでもありません。また、そんなに短いスパンでは、とても「こころの表現としてのことば」は身につきません。長い時間をかけて大切に大切に、心とともに育んでいくものだと思います。
もし、今、迷われている若いテューター(私もまだまだ若いつもりですが・・)、保護者の皆様がこの日記を読まれていたら、「迷っていたらもったいないですよ!」って、申し上げたいです。どうぞ自信を持って続けてください。日米のこどもの差はありますが、「ラボの言語習得方法は、間違っていないな!」って、アメリカでも実感できましたもの!!
ラボは30年以上の実績があり、多くのこども達が実際に育っています。このひろば@でも、それぞれのパーティの様子を知ることができますね。
(それでも、まだ、「う~ん」って唸ってらっしゃる方は、私のHPのラボ高校留学のページをご覧ください。3才から15年間ラボ活動をした子の英語のスコアーです。ラボでは、英語を点数ではかったりしないので、ラボっ子にとっても留学試験が初めて遭遇する点数化ですね。モチロンそれだけがすべてではありませんが、一般にはわかりやすいかと思い紹介します。中3の9月と12月の留学試験、留学出発前5月(高1)と帰国直前のものです。最後のほうにTOEFLのスコアに換算してあります。TOEFL600点獲得は相当難しいです。みんながみんなこうなるわけではありません。本人の努力があってこそ、です。でもその努力できる原動力は、どこから?って考えると、机の上だけでは絶対に足りないってわかりますよね。)
ほとんど宣伝していないラボに出会えたのも、きっとなにかのご縁ですし、どこか惹かれるものがあったからではないでしょうか?(私は、できたらラボっ子として出会いたかったほどです。)
どうぞ、ご自分の直感を信じてお進みください。きっと、「ああ、ラボを続けてきてよかった!!」っていえる日がきます。私達、テューターも、こども達やご父母の皆様にそういってもらえるように、日々鍛錬です!
****長い日記になりました。「書くも苦労、読むも大変」ですよね!
最後までおつきあいくださってありがとうございました。
偶然の出会いが、かけがえのない世界に広がっていきますように!
是非、一言、およせくださいね!!!
|
|
|
|
|
11月24日の地区発表会まで、あと20日!・・と、書いて「うわ~もうすぐ~」と急にあせり始めました。(毎年似たような状況ではありますが・・今年はかなり遅い展開!)各クラスの開催場所が遠いので、この合宿が勝負の合同2回目。
私はその前日、土曜日午前中:市教委の親子英会話教室(思いっきりラボ)とその参加者によるHalloween Party/午後:幼児クラスとお友達参加のHalloween big partyでヘトヘト状態だったので、「週明けに倒れるだろうなァ~」と覚悟を決めていざ合宿へ。今回の合宿の目標は、
①「ギルガメシュ王物語」に関して自分なりに決めた研究テーマをレポートし持ち寄る(小学校では「調べ学習」と呼び、今、盛んにやっているらしい)
②全員で全体の構成と伝えたいことを考え、具体的な表現をきめていく。
今年は、高校生がいないので中学2年生6名(全員国際交流から帰ってきたばかり。難しい年代!)がパーティリーダーです。
いつもは、誰よりもよく動き、誰よりも大声張り上げて・・パワー全開のしゃかりき“まじょまじょ”(私)もさすがに今回は体力の限界。思い切ってテーマ活動の進行を中学生にバトンタッチ!とはいえ、いささか心配で時折のぞきにいくのですが、、、「うわ、みんな楽しそう!」「皆が意見言ってる~」という状況にただただビックリ!小グループに分けて自分達がリーダーになってどんどん物語が進行しているではないですか。おしゃべり大好きで、いつも自分達だけで盛り上がっていた中学生のこの成長振り。とうとう私も「お呼びでない」状態になれたか?!
夜の小学生高学年ミーティング後、中学生は夜中までかかって細かな場面の再検討(世界一高い城壁のところといつもごちゃごちゃしちゃうパレードの場面とギルガメシュ・エンキドゥの闘いの場面、全員で言いたいセンテンスと、ナレーターが言うより登場人物が言ったほうが伝わるところの選び出し)をし、ゲーム内容を決め翌日に備えました。
ゲーム①進化論ジャンケン(ギルガメシュ編)
・・・農民⇒兵士⇒王様⇒太陽神
同じ身分同士でないとじゃんけんできない。勝ったら
一つ位が高くなる。農民には農民であることを示す表現
を予め決めておく。
②重さあてクイズ・・1チーム6人~7人、伝言ゲームの要領
で、リーダーから指示があった物・それがどのくらいの重さ
かを表現し次の人に伝えていく(声は出さない)
EX:シャボン玉・小麦袋5キロ・城壁の石30キロ他
ゲーム後に実際に30キロのラボっ子を持ち上げてみる。
「お、重い~ 」を実感。城壁作る時、皆、紙を持ってる
みたいに軽々持ち上げていた表現が、このゲームのおかげ
で腰が入るようになったよ!
③誰が、何してるゲーム
EX:「ギルガメシュがたたかっている」から少しづつ感情表現
をいれ、高度にしていく。
「男が苦しそうに太鼓をたたいている」
「シャマトが嬉しそうに歌を歌っている」など
~なかなか最後の人まで正確に伝わらない。ことばをつかわず
に表現することの難しさを全員かみしめた。
ゲームは全てグループ対抗。あまりに白熱しすぎて今回の合宿目標は全クリされなかったけれど、たてながグループの仲間が寝食共にしながら、目に見えないことばの世界をなんとかして伝えられるようにしていこうとする気持ちでいっぱいになった2日間。中学生の成長も、小さい子たちの頑張りもこういう機会があればこそ!忙しい毎日の中で、5000年前の物語とともにメソポタミア文明に出会える幸せ。なんて贅沢で豊かな時間なんでしょう。つくづく、ラボっ子って幸せなこどもたちなんだと実感。
そんなわけで週明けは、心地よい疲れです。(倒れなくてよかった!!)サポートしてくださった多くのお母様方に感謝申し上げます。
|
|
|
|
|
秋の地区発表会に向けて、やっとパーティの発表テーマが決まった!発表まであと1ヶ月半。かなり切羽詰った状態!合同1回目は、「ギルガメシュ大クイズ大会」これがまたかなりの難問続出で、テューターの私も、「へえ~」「わぁ~」「そうなんだぁ~」の連発。当日の参加者は小学1年生から中2。結構調べこんであったのでラボライブラリーだけじゃとても太刀打ちできない!(クイズは後述)*昨日入れられなかったこどもたちのクイズを最後の方に書き込みました。ちょっと長いですが最後までお付き合いくださいね!)
ところで、タイトルのシャマトのハープの件
「大英博物館の至宝展」が創立250周年と朝日新聞創刊125周年を記念して今週の土曜日からいよいよ東京都美術館(上野公園)で開催されます。すでにご存知の方も多いかと思いますが(もしかして、「ひろば」でもすでに話題になったかも・・・と思いつつ)、270点が5つの構成に分けて展示されます。まず導入部で大英博物館そのものの成り立ちの紹介。さらに世界を「古代オリエント」「ヨーロッパ」「アメリカ・オセアニア」「アジア」の4つの地域に分類。それぞれのコーナーで大英博物館を代表する品々を展示することにより世界を一周しながら旧石器時代以来1万年にわたる人類の文化遺産をたどる旅ができるという企画。
「古代オリエント」では、ウル(イラク南部)で出土した女王のリラ
が出迎えてくれるそうで、新聞広告や大英博物館のチラシやホームページにこのリラの写真が載っています。リラとは小型の竪琴で、メソポタミアに栄えたシュメール初期王朝時代の王族の墓から出土「ブ・アビ」という名の女王の墓の埋葬品で、牛の頭をかたどった金色の装飾とラビスラズリ、前面のパネルの貝殻の装飾が残っていて出土時に石膏でとった型をもとに復元されたそうです。発見された時、女王の手の骨が竪琴の弦のあたりに触れていたとか。
で~~~~、そうです。私が、このリラの載っているカラーのチラシをラボっ子に見せたら、「シャマトが弾いているハープに、この牛の頭とおんなじのがついてるよ!」っていうんです。で、あらためて絵本をじ~と見つめました。「ほっ、本当だぁ~」。シャマトが弾いているハープの下のほうに牛の頭の飾りが!!!
物語が「本物」につながっていくと、ぐっと臨場感が増しますね。
そういえば、昨年取り組んだ『十五少年漂流記』の時も、地図上でハノーバー島を発見した時は嬉しかったもんな~!
やっぱり、こどもってスゴイ!
どうぞ、皆さんももう一度絵本をじっくりご覧あれ。
で、ますます東京都美術館で本物のリラを、この目で見たくなりました。「東京までちょっと無理~」という方は、18日午後1時55分テレビ朝日で特別番組「大英博物館の七大秘宝の謎をとけ(仮題)がオンエアーされるそうですので、ナビゲーターの黒柳徹子さんと一緒に大英博物館を回ってみるのもおもしろそうです。
*牛頭のある女王のリラ/紀元前2600年~2400年ごろ/
写真及び詳細は、
http://www.asahi.com/daieihaku/gallery にあります。
************
ギルガメシュ合同1回目②
「ギルガメシュクイズ」について・・・
9月に、キーワードは「ギルガメシュ」「メソポタミア文明」「楔形文字」とラボっ子にふっておいたら、シュメール文明(ウル・ウルク・ラガシュなど多くの都市国家を形成)、バビロニア、ヒッタイト、アッシリアにまで広がり、文字の歴史やメソポタミアの神々までたどりついていた。私は、中1の世界史で習った『四大文明』のひとつがメソポタミア文明!でしかなく、そこから広がることはなかったものだから、改めてラボっ子をうらやましく思った。幼児・小・中学生年代で、人類最古の物語に出会えることの幸せ。そしてその物語の周辺をこんなふうに自分で調べて発見し発表できること。さらに、異年齢の仲間と再表現できる機会と場があること。なんて豊かで幸せな時間なんだろう!
ラボっ子からでたクイズ抜粋
①ウルクからティグリス川まで、何kmか?ティグリス川からみてウルクはどちらの方向か?
②メソポタミアの4つの文明を古い順に?
③フンババを倒す時に持っていた武器・剣・カブトのそれぞれの重さは?
④ギルガメシュのお父さんとお母さんは誰?
⑤シュメール語でギルガメシュはどんな意味か?
⑥楔形文字を発明したのはシュメール人。ではそのほかに人類初のものをたくさん作りました。それはなんでしょう?
⑦メソポタミアには、川や山や陶器などを司るありとあらゆる神がいました。では、イシュタル(シュメール語でイナンナ)は、なんの神?
★ラボっ子の答え
①約100キロ(甲府から東京までと同じくらい) 南西
②シュメール⇒アッカド⇒バビロニア⇒アッシリア
③各30kg
④母⇒ニンスン(太陽神シャマシュの神官)ギルガメシュは、このシャマシュから美しい姿を、嵐神(天候の神)アダトから男らしさを与えられた。(シュメール王名表より)
父⇒ルガルバンダ・ドウムジ(神格化されたウルクの王)
*ギルガメシュは紀元前2600年ごろ、シュメールの都市ウルクを126年間統治した実在の王。らしい
⑤「ギルガメシュ」は古バビロニア語以降の読み方で、シュメール語では「ビルガメシュ」(老人が若者である)という意味。らしい
⑥楔形文字のほかに・・A/暦(月の満ち欠けで年月をはかる太陰暦)
B/シュメールの七曜(旧約聖書の神が世界と人間を創造するところの1日目~7日目というのは、ココから出ている。(ノアも7日間!)
C/60進法
D/ハンコ・印鑑(円筒印章)中心に紐を通して首にかけるようになっていて、コレをかけている人は身分が高い。らしい
E/ビール
F/ワイン
G/彩文土器(土器に赤い模様)
⑦愛の女神(へぇ~~~~!)
*みんなで考える問題
a,ギルガメシュは、なぜ幸せではなかったのか?「幸せ」と感じる心がなければ「幸せではない」とも感じられないはずなのに・・・??
b,ギルガメシュは、神の力をもっている(神は3分の2?)なのにどうしてエンキドゥに負けたの?
c,エンキドゥは、自分を殺そうとしたギルガメシュをどうして助けたのか?
d,なぜ、ギルガメシュは、シャマトを好きでなかったのか?
だれも好きになれない「好き」ということを知らないのならなぜ、エンキドゥをおびき寄せるためにシャマトを送り込もうと思ったの?
e,イシュタールの求婚をなぜむげに断ったのか?
f、そもそもこの物語を語っている人は、誰?誰の視点で、見ているの?表現する時「しあわせではなかった」ってどうするの?
ギルガメシュがそう感じていないとするなら、どうすればいいの?
ひとつひとつ、みんなの思いをたぐり寄せていかなければなりません。
果てしない時間がかかりそうです。さて、どうなることか・・・
--------------------------------------------
|
|
|
|
|
2歳の息子さんを持つお母様の質問を受けて・・(初めて読まれる方
は、「ひろば」のトップページからテーマ【ラボにおける言語習得】をクリックして投稿の中から「英語のパスバンドは・・・」をお読みください。*パスバンドとは、優先周波数帯のことです。
ざわざわさんが、お答えくださっていることは、私も全く同感です。また、このページには様々な経験をお持ちの方がいらっしゃるでしょうから、特にラボ活動をしているお子さんをお持ちのお母様やテューターの皆様!是非ご意見を書き込んでいただきたいなと思い、日記から書き込むことにします。
****************
>私は「あいうえお」と一緒にアルファベットも教えたり、小さいうちから、英語の絵本などを見せて(文法は抜きにして)、
テキストにも親しませた方がいいと思っていました~。あと、簡単な単
語を書かせたりとか。(こういうことは、やらないほうがいいのでしょ
うか?)
⇒身体・運動・ことば・認識・感情・人間関係・・・こどもの能力の発達にはを大きな個人差がありますね。けれどもどの子もみんな伸びる力をもち、芽を出し、花を咲かせる時を待っています。そして、それを助けるのが、こどもに一番近いところにいるお母さん・お父さんの役目ですよね。それだけにどう助けるか、親の働きかけの適切さが重要なポイントになってきますから、気合はいります。
能力を発達させるというと、親はつい、早くから読み書き計算ができるというような目に見えるところに関心が集中してしまいます。でも能力というのは、こどもが本当におもしろがってやるから、その力が人間的な力として身についていくものであって、親が喜ぶとか、ご褒美がもらえる、できないとしかられるという理由で訓練される、言い換えれば調教されたような場合、一応能力は身につくでしょうがその根っこにその能力を使って何かをしたいという人間的な動機がないわけですから、現実には役立たなくなっていきます。
ですから、こどもの能力を伸ばす時に、書ける、読める、~ができる、という目に見えやすいことだけではなく、その能力を使ってその子の世界や生活がどう生き生きと広がってきているのかを親としてはいつも見ていく必要があると思うのです。
***************
⇒たとえば文字を覚える場合、大事なのは、まず、子ども自身の文字への興味を育むこと、こどもの中に「自分で字を書いてみたい!」という気持ちを育てていくことが大切だと思います。その場合「教え込もう」とすると、こどもはとたんに逃げていきます。その子が文字を使って何かを伝えたいというようなその子自身の要求があればその能力は自分のものになっていくと思います。
こどもが文字に関心を持つ時には、2つの段階があります。一つは
文字そのものがおもしろいな、とかコレはなんて読むのかな?と、一字一字に関心をもつというレベル。もう一つは、一字一字の文字には関心がないけれど、自分で本を読みたいとか、ママにお手紙を書きたいとか要するにある欲求があって、文字はその手段だというレベル。
どちらが先にきてもいいし、いずれどちらもやっていかなければなりませんが、その時この二つを混同しないほうが良いと思います。一字一字に関心を持った時に「じゃあこの覚えた文字で手紙を書こう」といわれたら、また何か教え込まれたという感じになってしまいますし、逆にお手紙を書いてみたいといった時に、「まず、あいうえおを覚えようね」といったら、せっかく何かをしたい欲求もしぼんでしまいます。いずれもその時点での子供の関心を尊重してあげることがだいじなのではないでしょうか。(これは日本語でも英語でも同じことです)
********
長くなりました。最後に研修で、大島清/京都大学名誉教授の書かれた文を読んだ時に、
【言語とは、すべての感覚で学ぶものなのである】というところに私は非常に感銘を受けたので、もしご参考になれば、、、と思い記します。
【ことばはことばだけで覚えさせるのではない。スキンシップをしながら[五感]の総てが言語に置き換えられることを学んでいく。これは大切な行為だ。転べば誰でも痛い。そこで、泣きながら「痛い」ということばを覚え、さらに痛くないように、転ばないようにという知識も学ぶ。このように身近にいるものからスキンシップを交えてことば学んでいくのに、早い段階で、勉強・学問としての言語教育に切り替えてしまう傾向が現代にはある。これが、情操教育に大きな影響を及ぼしている。
機械的に「学問」としての言語教育がされると、言語にまつわる感覚とか風景や臭いや感触などが言語に染み付かず、薄っぺらなものになってしまうのである。
言語は行動の規範になる。[五感]をフルに活用する共感覚として学ばなければ生きたことばにはならない。さまざまな感覚を含むことで生きたことばになる。生きたことばが自由に使えなければ、感動を思いのままに表現することも、喜びを身体で感じることもできなくなる。言語とは、総ての感覚で学ぶものなのである。】
|
|
|